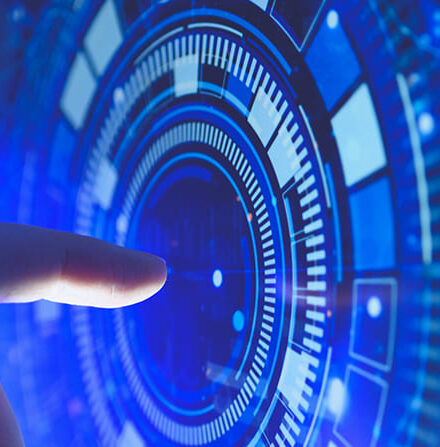(19)うれしい悲鳴
「時代の先へ」必死に進化
次々と改善バージョン投入
1985年2月に発売した「jX-WORD太郎」は価格が5万8000円。先行他社の半額だった。それだけでも驚かれたが、さらに翌年発売の「一太郎バージョン2」では既存ユーザーには下取りなしで3万円で売ることにした。多くの人たちに一太郎を使ってほしいと考えたのだ。
より多くの人に使ってもらうための戦略がバージョンアップだった。当初は3カ月ごとに次々と新バージョンを投入する計画だったが、さすがにそれでは開発が追いつかない。それでも他社が追随できないスピードを心がけた。
その中で重視したのがお客さんの声だった。一太郎のパッケージには、はがきを2枚同封した。ひとつは登録用。もうひとつがご意見用だ。ユーザーの声に耳を傾けて次のバージョンではどんな機能を追加すればいいのか、どう使い勝手を上げればいいのか。その参考にするためだ。ここにも一太郎が市場を席巻した理由があると思う。
ご意見用のはがきは狙い通りにたくさんの返信をいただいた。専用の棚を作り、整理係を雇ったほどだ。そのひとつずつに目を通し、お客さんが求めていることを一太郎の進化に落とし込んでいった。
こんな取り組みが功を奏し、バージョン2は7万6000本を超える販売を記録した。さらにその翌年の87年6月に発売したバージョン3は31万本もの大ヒットを記録した。3代目なのでファンの皆さんの間では「三太郎」の愛称で親しまれた。
我々の工夫も成功を支えた要因だろうが、ベースにあるのがやはりパソコン市場そのものの急激な伸びである。当時はまだ今のようなインターネットがないにもかかわらず、私が創業時に考えていた一人一台の時代に着実に近づいていることが実感できた。
起業する際には吉野川の流れに自分の人生を見立てたことは、本稿で何度か触れた。流れの中で木にしがみつき、自分の手で水を漕(こ)ぐことができれば、時代のさらに先を行けるだろう、と。
この頃は日々の仕事に忙殺されて過去を振り返る余裕がなかったが、今思えば確かに私はコンピューターという時代の流れの中で一太郎という大木をつかみ、さらに先を行こうと必死に手を回して漕ぎ続けていたのだと思う。
こんなこともあった。85年に一太郎をリリースした後のことだ。本社のある徳島市から吉野川を遡った池田町で、社員たちと次版に向けた戦略会議を開いていた。すると、留守番の女性から電話が入った。
「社長、大変なことになっています。早く帰ってきてください」
なにごとかと思いきや、封筒の開封が間に合わないのでという。当時はバージョンアップしたお客さんからの支払いは現金書留で送金してもらっていた。人の高さほどの大きな棚を書留封筒を入れる金庫代わりに使っていたのだが、とうとう開封作業が追いつかず封筒が入らなくなったのだ。さらに聞けば、開封するハサミを扱う右手の中指が擦り切れて痛いとも。うれしい悲鳴とはこのことだ。
かつての教え子に誓った「日本一」の目標は、かなえられた。もっとも、今も初子には「あの時、世界一と言っていれば」と言われる。確かにその通りかもしれない。ただ、当時の私たちにはまだまだ日本でやるべきことがあった。この国でコンピューターを進化させ、知的生産性を高めることに貢献するために。

「一太郎バージョン3」のフロッピーディスク